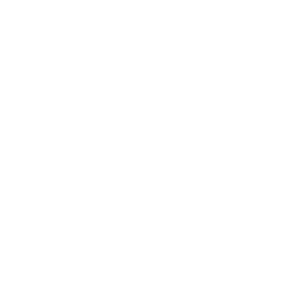7月2〜3日にかけて、北八ヶ岳の双子池ヒュッテにて、ハンモック専用キャンプサイトの整備活動に参加してきました。
「ハンモック専用サイト」と聞いても、まだピンとこない方が多いかもしれません。というのも、ハンモックといえば南の島のリゾートやお昼寝、遊具としてのイメージが強く、あくまで“あると嬉しい”サブ的な存在として捉えられがちです。
しかし、私自身が日頃から多方面でヒアリングを重ねてきた中で、ハンモックは老若男女問わずほとんどの人が「知っている」道具であるにも関わらず、実際に「体験したことがある」人は1割にも満たないという、非常にユニークなポジションにあると感じています。

ハンモックの起源とキャンプスタイルの変化
多くの人にとって、ハンモックは「日中のんびり休むもの」という印象があると思います。しかし、その起源は中南米の先住民たちが寝具として使っていたことにあります。高温多湿の環境でも快適に、そして地面から離れて動物や毒虫の被害から身を守れる実用的な寝具として、世界に広まりました。
「キャンプ=テント」というイメージが強い中で、「ハンモックで寝るの?」という疑問もあるでしょう。ですが、ここ5年ほどで日本国内でもハンモックスタイルのキャンプがじわじわと広がってきています。
このスタイルは、北米のロングトレイル文化に端を発しています。ハンモックは、
- 地面に優しい(整地不要・ダメージが少ない)
- 軽量・コンパクト
- 設営・撤収が簡単
- 汚れにくい(地面に接しない)
といったメリットがあります。一方で、プライバシーの確保や悪天候時の対応には工夫が必要で、ある程度の経験者向けスタイルとも言えます。

双子池ハンモックサイトの特徴と整備活動
このようなハンモックキャンプを山岳エリアで本格的に体験できる場所は、全国的にも珍しく、双子池ヒュッテはその貴重なひとつです。
ヒュッテ周辺には、自然の地形や樹木を活かして整備されたハンモック専用サイトが設けられており、「山を旅する新しい宿泊スタイル」を実践できる場所となっています。
特にこのサイトのメインテーマとして掲げられているのが、
- 「本来の形をなるべく崩さない(環境保全)」
- 「個人のアウトドア体験を尊重する(パーソナルスペースの確保)」
という2つのコンセプトです。




手を加えすぎず、自然のままの地形を生かしながら設営する。そして、隣のサイトと適度な距離を保ち、静かな時間や個人の自然体験を大切にするという考えが、サイト設計の根底にあります。
今回の整備活動では、ヒュッテのスタッフ、アウトドアショップやメーカー関係者、コアなハンモックユーザーなど、計9名が参加し、サイトや通路の補修を行いました。
資材はすべて現地調達。倒木、落ち枝、石、土を活用し、自然の力を活かした整備を手作業で進めました。雨水の流れや地形の傾斜を読みながら倒木を配置し、自然に土砂が堆積・再生していく構造を作るという手法です。
今回も、トレイル研究家・勝俣さんの指導のもと、「自然と共生する整備のあり方」を学びながら作業を進めることができました。

サイト環境の変化と課題
昨年10月にもこの活動に参加しましたが、今回現地を歩いてみてフィールドの変化に気づきました。
特に気になったのが、本来通路ではない笹のエリアが踏み荒らされていた点です。おそらく、自分のサイトへ戻るために近道として笹エリアを踏み越えている人が多く、その結果、笹が枯れ、土がむき出しに。さらには雨で土が流れ、サイトの下側が大きく浸食されていました。


「ただの足跡」から始まった変化が、たった10ヶ月でここまで景観を変えるとは衝撃でした。このまま放置すると、サイト自体が使いにくくなってしまいます。
そこで今回の活動では、ハンモックサイトと通路の明確化、そして笹エリアの再生に注力しました。
これは登山道整備と同じで、「境界を守る」ことの重要性を改めて感じました。ユーザーの意識が変わらなければ、いずれはこの素晴らしい景観が失われてしまうかもしれません。

未来へつなぐハンモックキャンプ文化
ハンモックサイトは「不整地でも木があれば成立する」柔軟性が魅力です。これは山岳エリアにおける新たな宿泊スタイルとして、非常にポテンシャルを感じます。
参加メンバーの間でも、「このようなハンモックサイトがもっと全国に増えて、日本の山々をハンモックで旅できたら楽しいね!」と大いに盛り上がりました。
整備活動は、ただの作業ではなく、未来にこの素敵な空間を残すための大切な一歩です。今後も引き続き、この取り組みを続けていきたいと思います。


堀田貴之氏